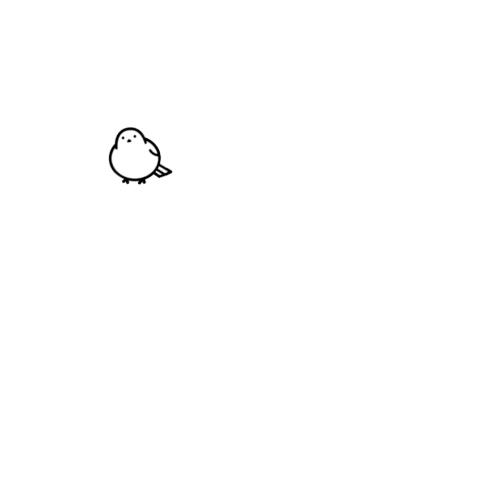GIGAスクール構想
特別支援×ICT
教員のICT活用指導力チェックリスト
学校DX化でわくわくをサポート
熊本大学教育学部特別支援教育本吉研究室による授業・教材研究を支援する情報プラットフォームです。生成AIを活用した指導案や個別の指導計画の作成支援や教材作成、アセスメントなど様々なツールが公開されています。
本研究はJSPS科研費(課題番号23K02737)の助成を受けて実施されており、研究成果報告にはユーザーからの評価が必要です。チャットボットご使用の際は、アンケートへ(1分程度)のご協力を募っています。
長野県特別支援教育 ICT活用支援サイト
「ICT活用の観点(国立特別支援教育総合研究所)」を基に分類された実践データベースや教材教具データベースが公開されています。また、特別支援教育におけるICT活用の視点や学習場面におけるICT活用の観点から活用段階が示されており、根拠のあるICT活用に関する情報が公開されています。
おすすめGIGAスクール構想
【文科省】学校におけるICT活用について
- 効果的なICT活用に向けた取組
- ICTの効果的な活用に関する資料等について
- その他
ガイドライン等
関連情報
教育委員会等向け事務連絡
ICTの効果的な活用に関する参考資料
- iPad活用に関する資料(Apple社)
- Google for Education活用に関する資料(Google for Education)
- Microsoft Education活用に関する資料((株)日本マイクロソフト)
StuDX Style(スタディエックス スタイル)
"すぐにでも" "どの教科でも"
"誰でも"活かせる1人1台端末の活用シーン
≫内容の一部紹介はここをクリック
GIGAに慣れる
毎日の振り返りの記述でタイピング力UP
デジタル付箋を使ってみよう
スピーチ練習に音声認識学習環境づくり など
教師と子供がつながる
家庭学習カードのオンライン化
「朝ノート」で健康観察
翻訳機能を使ってサポート など
子供同士がつながる
付箋操作のオンライン化
コメント機能を活用した学び合いの活性化 など
学校と家庭がつながる
個人懇談日程の希望調査をオンライン化
保護者へのお手紙
オンライン説明会の実施(進路説明会・修学旅行説明会) など
職員同士でつながる
職員会議のペーパーレス化
クラウドで共同編集
クラウドを活用した初任者研修 など
特別支援×ICT
 チャンネル
チャンネル
-
特別支援教育の何でもチャンネル
NEW
特別支援教育でiPadの活用に関する動画が提供されています。iPadのアクセシビリティはおすすめです。
特別支援教育と支援技術金森克浩さんによる特別支援教育における支援技術を利用するための、動画コンテンツ活用のWebサイトです。カテゴリー別に動画が整理されていて、検索しやすくなっています。
Toku-Navi
新大附属特別支援学校の授業解説動画です。
(パンフレットより)「特別支援教育って何だろう?」「特別な支援が必要な子どもへの授業ってどうすればいいんだろう?」「この子にはどんな支援が必要なのだろう?」等、特別支援教育に関わる誰もが知りたい内容を、特別支援学校の現場で活躍する教員がわかりやすく紹介します。
新潟市障がい者ICTサポートセンターの山口さんのYouTubeチャンネルです。
174iamsamチャンネル福岡県今津特別支援学校の元教員、福島勇さんのYouTuberチャンネルです。ICT機器活用に関する動画をたくさん公開しています。
文部科学省/mextchannel【再生リスト】始めよう遠隔教育
詳細
-
初級編
中級編
上級編
【再生リスト】遠隔教育事例紹介
詳細
-
A1 遠隔交流学習
A2 遠隔合同授業
B1 ALTとつないだ遠隔学習
B2 専門家とつないだ遠隔学習
B3 免許外教科担任を支援する遠隔授業
B4 教科科目充実型の遠隔授業
C1 日本語指導が必要な児童生徒を支援する遠隔教育
C2 児童生徒の個々の理解状況に応じて支援する遠隔教育
C3 不登校の児童生徒を支援する遠隔教育
C4 病弱の児童生徒を支援する遠隔教育
D 家庭学習を支援する遠隔・オンライン学習
E 遠隔教員研修
個人/団体サイト・ブログ
-
note あっきーの教材工房
iPadアプリ「ごじゅーおん」や「えにっき」「たっち&びーぷ」など数々の教材アプリの開発者AKIHIRO SUZUKIさんのnoteです。アプリの機能に関する機能の説明や使い方などの情報が紹介されています。
ドロップレット・プロジェクト特別支援教育の場で広く活用されているシンボル「ドロップス」を始め、AACアプリ「DropTalk」や「DropTap」を開発しているドロップレットプロジェクトがサイトをリニューアルしました。新たなサービス「DropNews」や「Drop-In」の開設など進化を続けています。
マイスイッチ(サイトより要約)病気や障害のため腕や指の動作がうまくいかない方々が身体の状況に合わせた様々な「入力スイッチ」を活用して電子機器を上手に使うためのノウハウや事例を紹介するページを開設しました。
佐賀のLAN(サイトより)「佐賀県情報端末・AT(アシスティブテクノロジー)利活用研究会」(通称:佐賀のLAN)では、佐賀県で整備されているICT機器や、その他のアシスティブテクノロジー(支援技術)の利活用について、特別支援教育に携わる教員や、コ・メディカルを中心に、情報共有をする活動をしています。
NPO法人ICT救助隊(サイトより)難病患者や重度障害者の方のコミュニケーションを、ICT(情報通信技術)を活用して支援するNPO法人です。
井上賞子さんのnote(サイトより)まんがに日々癒されて半世紀近く(^◇^;) 好きなまんがの紹介と、子ども達が学習する時に役立つアプリの紹介をのんびりしていきます^_^
コミュニケーション支援ブログ
(サイトより)聞いてみる-「どんな支援ツールがあるのか教えて欲しい」「当事者さんのニーズにあった支援機器ってなんだろう」「マウスが使えないからスイッチ入力にしたいけどやり方がわからない」などなど、誰に聞いたら良いかわからないお悩みがあれば、ぜひご相談ください。
検索してみる-「講習会の案内」「機器を使う際のポイント」などなど。「検索」「カテゴリー」「タグ」などを活用して、気になる記事を読んでみてください。投稿記事からは、投稿者へ質問も可能です。
(サイトより)「魔法のプロジェクト」は携帯情報端末を実際に教育現場でご活用いただき、その有効性を検証し、より具体的な活用事例を公開していくことで、学ぶ上での困りを持つ子どもの学習や社会参加の機会を増やすことを目指しています。
kintaのブログANNEX(サイトより)金森克浩の個人的なブログです。このサイトに書かれていることは,金森の個人的なものです。マジカルトイボックスの活動紹介やAT,AAC,ICTに関わる情報を発信しています。
Sam's e-AT Lab(サイトより)障害による困難さのある子どもたちの学習や生活を豊かにするためのe-AT(electronic and information technology based Assistive Technology=電子情報通信技術をベースにした支援技術)に関する話題
ポランの広場 福祉情報工学と市民活動視線入力
(サイトより)島根大学総合理工学研究科 助教
伊藤史人(ふみひと)の主宰サイトです。
主に重度の障害者に関連した福祉&工学系の情報を掲載しています。
視線入力アプリ「EyeMoT」シリーズの活用情報やダウンロードはこちらです。
(サイトより)身の回りにあるテクノロジーの便利な活用方法を紹介し,発達障害・学習障害(ディスレクシア・ディスグラフィア)のある子どもたちのためのテクノロジー・ICTを使った新しい学び方を提案していきます。
NPO法人 支援機器普及促進協会(ATDS)
代表の高松崇さんの各種講演資料が多数公開されています。
(サイトより)毎日の生活のなかでの、ささやかな「やりたいこと」。
好きな本を読んだり、親しい人とことばを交わしたり、近所のお店に一人で出かけたり——
それは、ちいさなようで、たいせつな想いです。
そしてそれは、もしかしたら明日はできる「可能性」かもしれません。
DAISYやアクセシブルなEPUB3のリッチコンテンツの普及と研究・開発、点字のモバイル情報端末を活用した盲ろう者の情報支援等を中心に活動しています。
(サイトより)ATDO(支援技術開発機構)は、障害者や高齢者の情報へのアクセスとコミュニケーションに関わる分野における、支援技術とユニバーサルデザインの開発、またそれを活用した支援を行うために2006年4月に発足した団体です。
(サイトより)障害のある若者に、テクノロジー活用を主として、自らのニーズに適した方法で学ぶこと、自分の希望する進学先へ進学すること、自分が希望するキャリアにつながる力を育てること、に関連する、様々なプログラムの提供を、継続的に実施しています。プログラムに参加した障害のある若者たちが、社会進出し、社会のリーダーとなることを期待し、活動を続けています。
LEARN(サイトより)LEARN:[Learn(学ぶ), Enthusiastically(熱心に), Actively(積極的に),Realistically(現実的に),Naturally(自然に)]は、子どもたちがありのままの自分でもいいんだと安心すると同時に、学びの面白さや自由さに気づいてもらうこと,子どもたちが自由に行き来できるような、今の公教育を補完するもう1つの教室をつくることをねらいとして。現在の学校教育と違った学びを提供するプログラムです。
かながわ障害者IT支援ネットワーク(サイトより)障がいのある方のIT活用を支援するため、『神奈川県障害者IT利活用推進事業』を運営しています。 当サイトは、IT活用をサポートする情報をわかりやすくお伝えします。